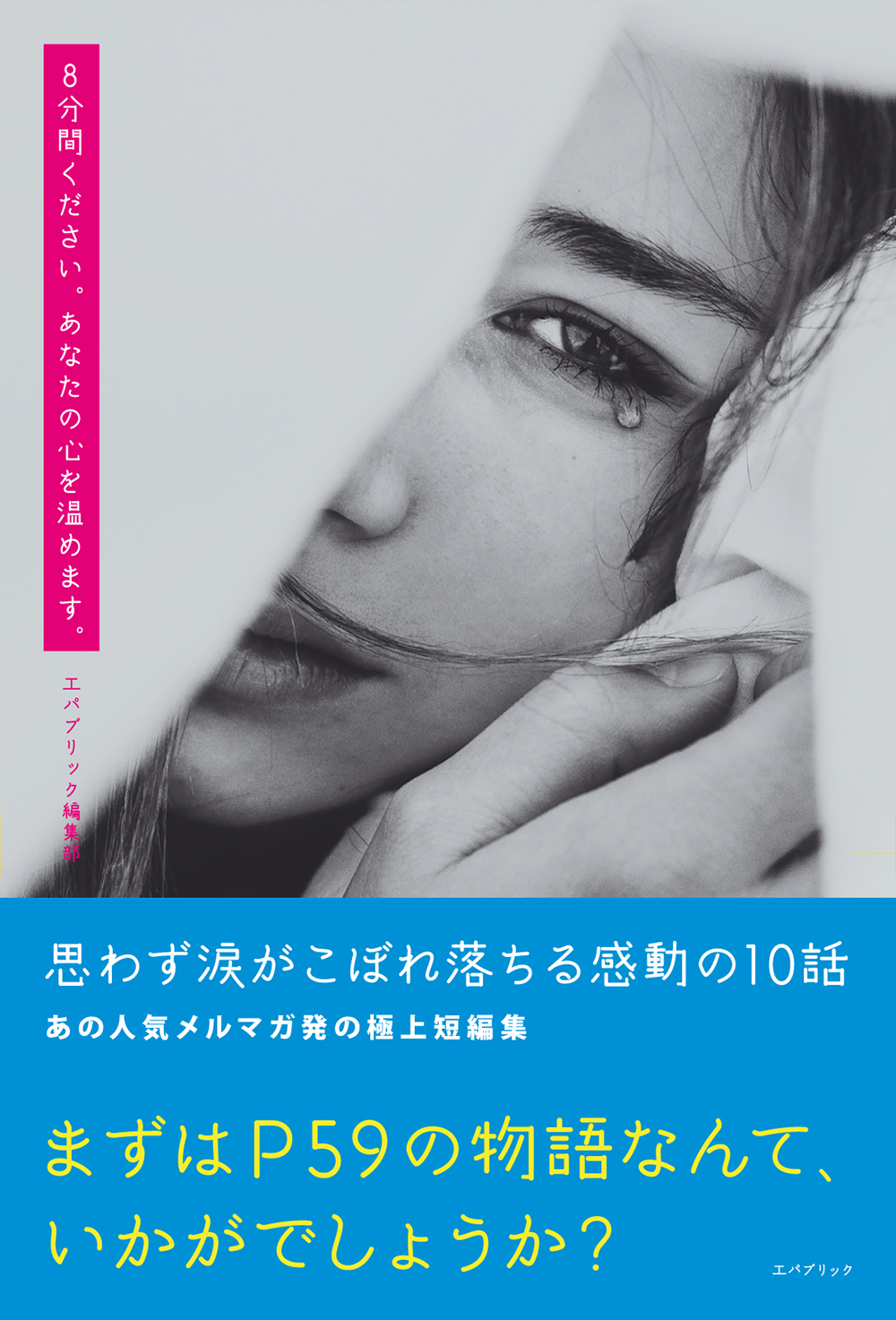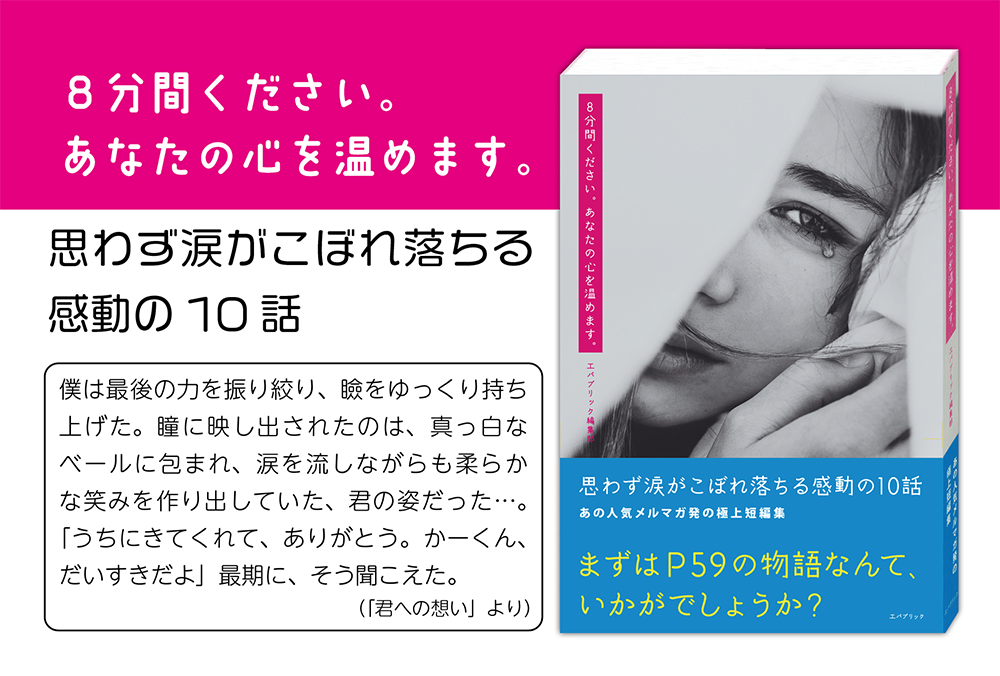僕は最後の力を振り絞り、瞼をゆっくり持ち上げた。
瞳に映し出されたのは、真っ白なベールに包まれ、涙を流しながらも柔らかな笑みを作り出していた、君の姿だった……。
「うちにきてくれて、ありがとう。かーくん、だいすきだよ」
最期に、そう聞こえた。
(「君への想い」より)
トンネルを抜けて、パッと車内が明るくなった。ローカルバスの低い音が響く中、窓の外に目を向けるときらめく海が広がっていた。
乗客は私ひとり。こんな寂さびれた田舎をわざわざ訪れる者はいない。私だって一五年ぶりのずっと避けてきた故郷だ。
父の死の知らせが来るまでは。
(「描きかけの夢」より)
甲子園に行くのが夢だった。
県大会決勝戦が終わったその日の夜、帰宅してからすぐに自室へ籠こもった俺は、ベッドに腰かけて座っていた。部屋は暗く、ため息とクーラーの稼働音が反響するばかりだ。
「はぁ……」
頭の中で繰り返される今日の試合内容に、またため息が漏れる。それがイラ立ちを生んで舌打ちをしてしまい、自己嫌悪から両手で顔を覆おおって沈んだ。
あと一歩だった。決勝まで進んだのに、最後の最後で二対三で敗れた。甲子園に行けるはずだった。けれども届かなかった。
(「決勝戦の夜」より)
横からシャッター音が聞こえた。
寒風が肌を刺す屋上の柵越しに、アタシが世界を見下ろしていたときだ。
にらみつけるようにそちらへ視線を向けると、貧相なおっさんが高価そうなカメラをこっちに向けて構えていた。
「あまりにもかっこいい表情だったから、ついつい撮っちゃったよ」
はげ散らかした頭、乾き切ったカサカサの肌とは対照的な、満面のスケベそうな笑み。
「クールビューティーもいいけど、もっと違った顔……笑っているところも見てみたいな。もちろん被写体になってくれたお礼はするからさ」
お金でアタシを買う気か? というより勝手に撮るな。
(「ぽうとれいと」より)
本書に収録されている作品は「小説予備校」メールマガジンの読者デビュープロジェクトで募集した「読後、温かい涙が流れるような五〇〇〇文字以内の小説」に投稿された作品から選んでいます。
そもそも「小説予備校」メールマガジンはまだ世の中から発見されていない才能を見つけ出して一人ひとりの力を最大限に引き出し、そして世の中に広めるために始めたもの。
ですので、収録作はすべてこれまでみなさんが出会ったことのない才能達が紡ぎ出した物語です。
「小説予備校」メールマガジンでは「これから小説を書きたい」という初心者から「はやくプロ作家として活躍したい」というプロ志向の人まで幅広い方々にご愛読いただいております。
もしもご興味があるようでしたら一度ご覧ください。
これからも次々と本書のような作品を発表していく予定です。